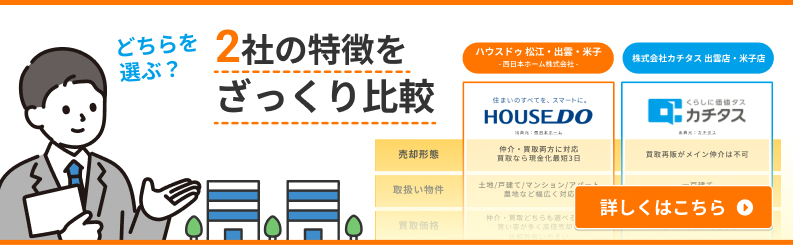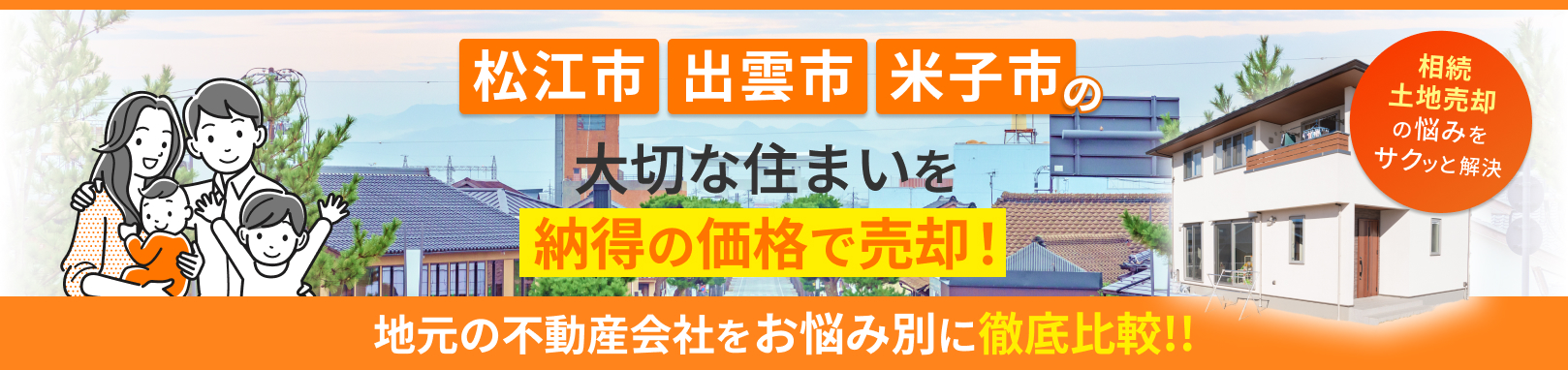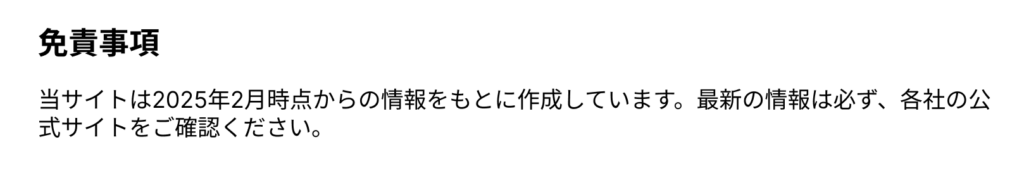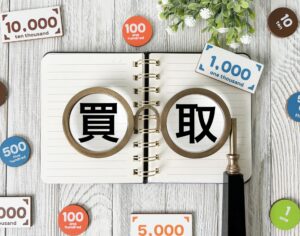不動産を売却した後の固定資産税については、曖昧なまま売却に踏み切ってしまう方もいるでしょう。固定資産税には1月1日時点の所有者に課税されるというルールがありますが、売却時には「日割り精算」という方法を用いて、売主と買主の間で公平に負担を分けるのが一般的です。
この計算方法を理解しておくことで、事前に資金計画を立てやすくなり、想定される出費に対して準備ができます。
本記事では、不動産売却に伴う固定資産税の支払い義務や計算方法をわかりやすく解説します。税金面の不安を解消し、スムーズな売却につなげるための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
また、以下の記事では山陰エリア(松江市・出雲市・米子市)の不動産売却をする際のおすすめの会社を紹介しているので参考にしてください。
固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人に対して、毎年課される地方税の一種です。課税対象となるのは、1月1日時点で登記上の所有者となっている人であり、自治体が発行する納税通知書に基づいて支払う義務が生じます。
税額は、固定資産の評価額に税率(標準税率は1.4%)をかけて算出されます。不動産を売却する際には、この固定資産税の負担について「いつまでの分を誰が支払うのか」という点が問題になることがあります。
特に年の途中で売却が行われる場合、税の支払い期間と所有期間が一致しないため、売主と買主の間での負担調整が必要となります。そこで用いられるのが、固定資産税等清算金という仕組みです。
固定資産税等清算金とは

固定資産税等清算金とは、固定資産税や都市計画税といった年間の税負担を、売主と買主の間で日割り計算により公平に分担するための金銭のことを指します。
日本では固定資産税が1月1日時点の所有者に課されるため、その年の税額は原則として売主が全額支払うことになります。しかし、実際には引き渡し日以降の期間は買主がその不動産を使用することになるため、税の負担を一部買主が負担するのが一般的です。
この清算制度を活用することで、売主は実際の使用期間に応じた分だけの税金負担で済み、買主も不動産取得後に不公平な税負担を負う心配がありません。
不動産を売却した年の固定資産税は誰が払う?

不動産を売却した年の固定資産税は、原則として「1月1日時点の所有者」に課されます。つまり、年の途中で売却したとしても、納税義務は売主にあります。自治体が毎年4月から6月頃に発行する納税通知書も、登記上の所有者である売主に送付されます。
ただし、物件の引き渡し後は買主が不動産を利用することになるため、年間の税負担を売主がすべて負うのは公平とはいえません。そこで多くの不動産取引では、固定資産税を売主と買主で「日割り清算」することが一般的です。
清算方法については契約時に取り決めがなされ、売買代金とは別に精算金をやり取りする形で調整します。この精算によって、お互いに納得のいく形で税負担の公平性が保たれます。
2種類の起算日

固定資産税の精算においては、清算期間の「起算日」をどこに設定するかが重要です。実務では、主に2つの起算日が用いられており、不動産会社や契約当事者の合意によりいずれかが選ばれます。
1つ目は、1月1日起算です。この方式では、暦年の初日から引き渡し日までを売主負担、それ以降を買主負担となります。1月1日起算はもっとも一般的で、納税義務者の原則にも合致しているため、多くの取引で採用されています。
2つ目は、4月1日起算です。これは固定資産税の課税年度(4月~翌年3月)に基づいて清算されます。実際の税額通知が自治体から届くタイミングと一致するため、実務上の精算がしやすい点が特徴です。ただし、売主と買主の合意が必要であり、事前に起算日の確認をしておくことが大切です。
いずれの方式を選ぶにしても、売買契約書に明記することがトラブル防止につながります。
固定資産税の日割り清算とは?

不動産を売却する際、年の途中で所有者が変わるため、固定資産税は売主・買主で日数に応じて分担します。この取り決めが日割り清算です。
所有期間に基づいて税額を公平に分けることで、売却後のトラブルを防ぎ、双方が納得できる形で不動産取引を進めることが可能です。
日割り清算のシミュレーション(6月30日に不動産を引き渡した場合)

以下では、日割り清算のシミュレーションを行います。条件としては、6月30日に不動産を引き渡した場合を想定し、以下の2パターンの起算日です。
それぞれの日割り計算のシミュレーションについて見ていきましょう。
1月1日を起算日とする場合

1月1日を起算日とする場合、その年の1月1日から引き渡し日である6月30日までを売主負担、それ以降の7月1日から12月31日までを買主負担とするのが一般的です。
例えば、年間の固定資産税が120,000円だった場合、1年は365日であるため、1日あたりの税額は約328.8円となります。この税額にそれぞれの負担日数を掛けて計算します。
- 売主の負担期間:1月1日〜6月30日(181日間)
→ 328.8円 × 181日 = 約59,513円 - 買主の負担期間:7月1日〜12月31日(184日間)
→ 328.8円 × 184日 = 約60,307円
この場合、実際に納税義務があるのは売主となるため、決済時に買主から売主へ60,307円を固定資産税等清算金として支払う形になります。これにより、所有期間に応じた負担が公平に実現されます。
4月1日を起算日とする場合

4月1日を起算日とする場合は、固定資産税の課税年度(4月1日~翌年3月31日)を基準に日割りします。この方式は、自治体が税金を計算する年度に合わせているため、事務処理がしやすいという特徴があります。
例えば、年間の固定資産税が120,000円、1日あたりの税額が約328.8円とすると、課税年度における清算は以下のようになります。
- 売主の負担期間:4月1日〜6月30日(91日間)
→ 328.8円 × 91日 = 約29,919円 - 買主の負担期間:7月1日〜翌年3月31日(274日間)
→ 328.8円 × 274日 = 約90,661円
この場合も納税義務者は売主ですが、実際に使用する期間に応じた税額を買主が清算金として負担します。起算日を4月1日とする方式は、特に年度単位での予算管理を行っている場合や、自治体との整合性を重視する場合に用いられます。
どちらの起算日を採用するかは契約時に確認し、売買契約書に明記しておくことが重要です。
固定資産税以外で清算できる費用
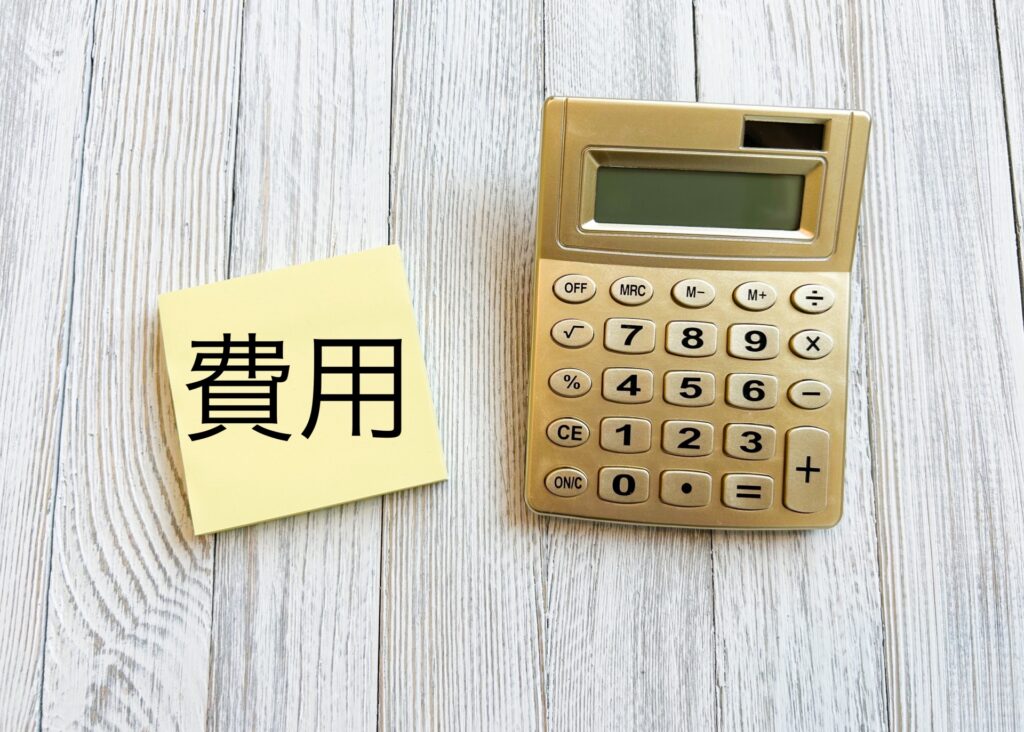
不動産売買において清算の対象となるのは、固定資産税だけではありません。実務では、不動産の維持や管理に関連する費用についても、日割りまたは月割りで売主と買主の間で精算するケースが一般的です。
代表的なものとしては、以下の2つです。
特に管理費や修繕積立金は月単位での徴収が多いため、月末・月初の引き渡し時には注意が必要です。それぞれの費用について解説していきます。
都市計画税
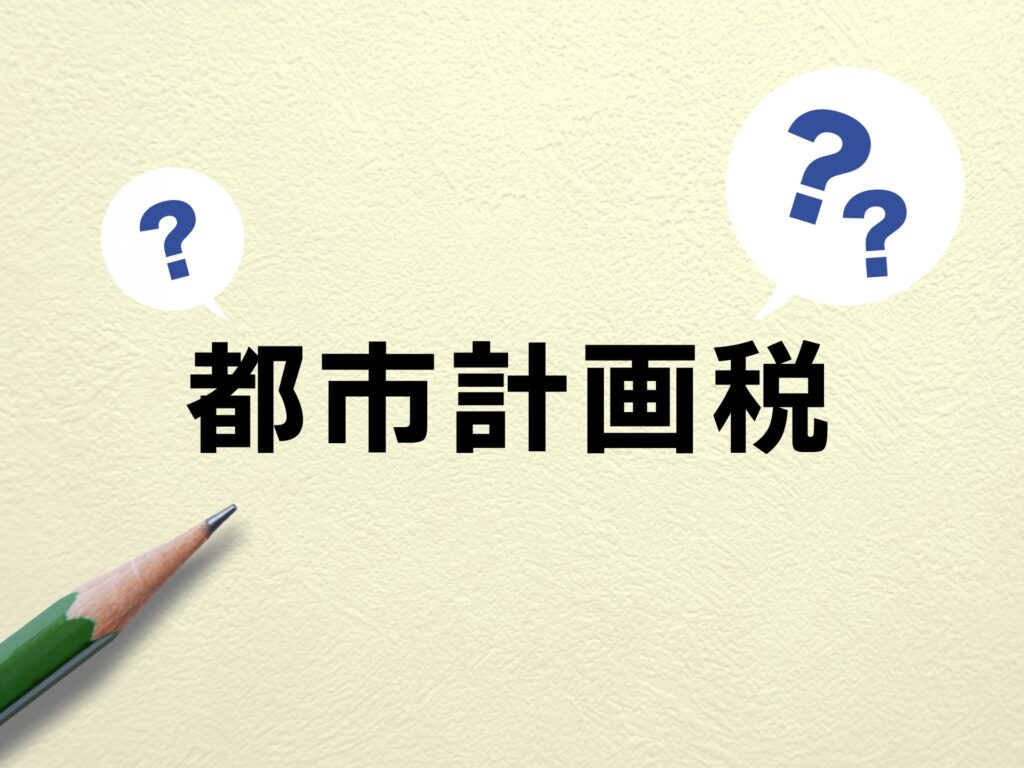
都市計画税は、固定資産税と同様に毎年1月1日時点の所有者に課される地方税で、市街化区域内にある土地や建物に対して課税されます。税率は最大で0.3%とされており、固定資産税と一緒に納税通知書で通知されるのが一般的です。
不動産売却の際には、この都市計画税も固定資産税とあわせて「固定資産税等清算金」として精算されます。例えば、引き渡し日が6月30日の場合、1月1日から6月30日までの期間は売主が負担し、それ以降の期間については買主が清算金として売主へ支払うことになります。
都市計画税の精算は、固定資産税と一体で計算されるため、個別に分けて金額を出す必要はありませんが、契約書には「固定資産税および都市計画税を対象に日割り精算を行う」など明確な記載が必要です。
管理費・修繕積立金

マンションや一部の分譲住宅などの区分所有物件では、管理費や修繕積立金の清算も必要になります。これらの費用は、建物の維持・管理や将来の大規模修繕に備えるために、月ごとに所有者へ課されるものです。
売却にあたっては、引き渡し時点での所有期間に応じて、管理費や修繕積立金を月割りで精算するのが一般的です。
ただし、管理会社によっては当月分を先払いしているケースもあり、その場合には「売主が支払済みの費用の一部を買主が清算金として支払う」という形で処理します。逆に、未払いがあれば売主が決済時に支払う必要があります。
こうした清算は、売主・買主の双方にとって公平性を保つために欠かせません。契約書や重要事項説明書の中で、金額や精算方法を明確に記載しておくことで、取引後のトラブル回避につながります。
固定資産税を支払う際の注意点

不動産売却において、固定資産税の取り扱いには注意点があります。具体的には、以下の通りです。
これらをあらかじめ把握しておけば、売買後のトラブルや誤解を防ぎ、スムーズな引き渡しにつながります。それぞれの注意点について解説していきます。
1月1日時点の所有者が納税義務者となる
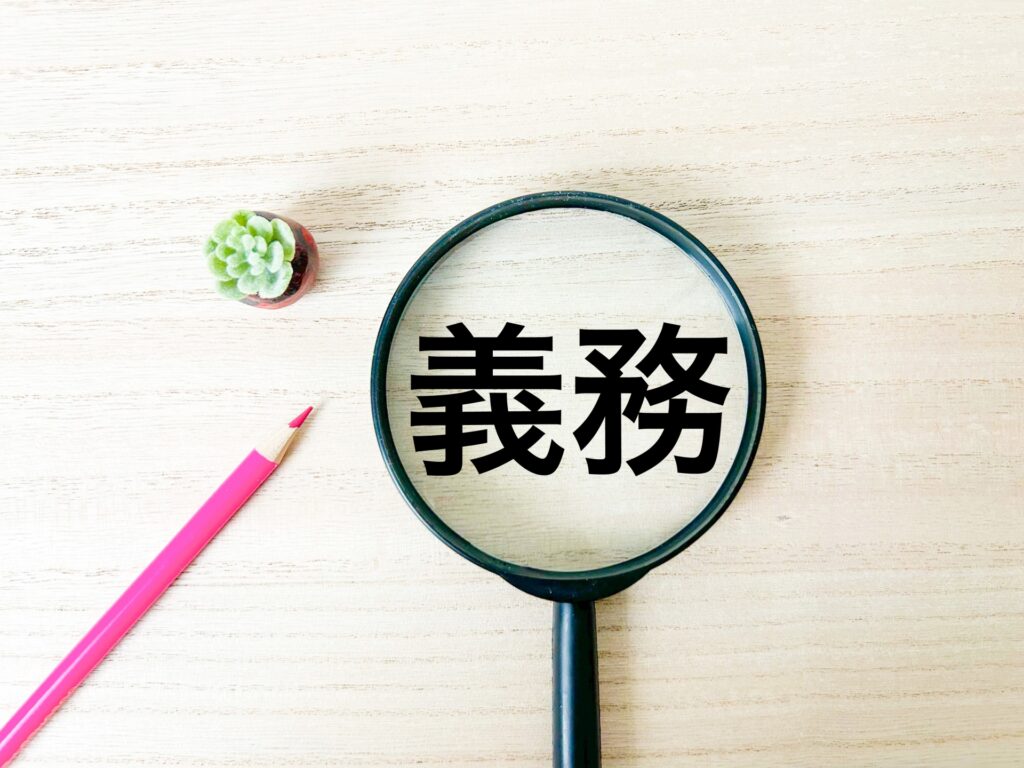
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人に限定されます。これは地方税法に定められており、年の途中で所有権が移転したとしても、税務上の納税義務は変更されません。
そのため、3月や6月に不動産を売却した場合でも、1月1日には売主が所有者であるため、その年の固定資産税は売主に全額課税されます。買主には納税義務は発生しません。納税通知書も売主宛に送付され、売主が自治体に対して税金を納める形となります。
この原則を誤解してしまうと、売却後に「税金が届かない」「誰が払うべきか分からない」といった混乱が生じるおそれがあります。そのため、契約時に固定資産税の取り扱いを明確にし、納税義務の所在を正しく理解しておくことが大切です。
日割り清算に法定義務はない

固定資産税の日割り清算は、実務上は一般的に行われていますが、法的な義務があるわけではありません。つまり、清算を行うかどうかは売主と買主の合意によって決まるものであり、契約書での取り決めが重要になります。
仮に清算の合意がない場合、売主が年間税額を全額負担し、買主は一切支払わないという形も成立してしまいます。これは売主にとって大きな負担となる可能性があるため、事前に不動産会社を通じて清算方法を協議し、契約条項として明記することが推奨されます。
また、契約時に「清算する」と口頭で話し合っていたとしても、書面上で記載がなければ、後から請求するのは難しくなるでしょう。税金に関するトラブルは取引の信頼性にも関わるため、法的義務がないことを踏まえた上で、契約書での明文化を徹底しましょう。
納税通知書は売主に届く
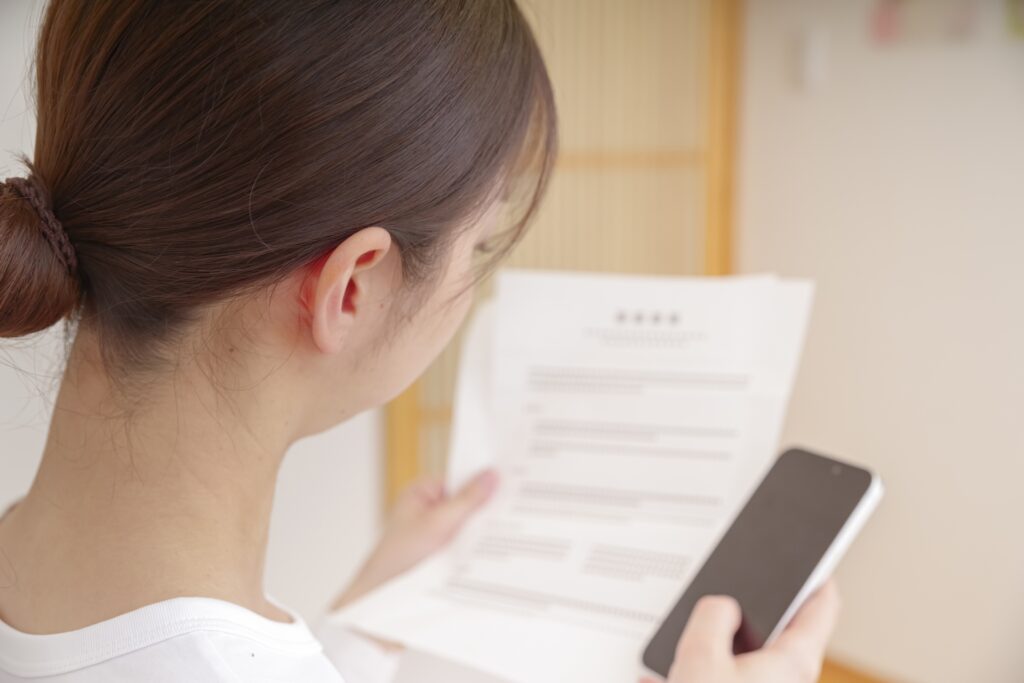
固定資産税の納税通知書は、登記上の所有者である1月1日時点の人物、つまり売主のもとに届きます。引き渡し後であっても、税務上の所有者変更は即座には反映されないため、通知書が買主に送付されることは基本的にありません。
そのため、売主は売却後も納税通知書の内容を確認し、納期限までに納付を済ませる必要があります。また、買主が支払うべき分を日割りで精算していた場合には、その金額を考慮して自己負担額を確認することが必要です。
通知書が届かない、あるいは新住所に転送されないといった事態も想定されるため、売主は引っ越し後の住所変更手続きや、納税スケジュールの把握を怠らないようにしましょう。
売買契約時に清算金を受け取る場合は前年の納税額から仮精算される

売買契約時に固定資産税等清算金を受け取る際には、実際の税額がまだ確定していないケースがあります。そのため、清算金の算出には前年の納税額を基にした仮精算が行われます。
例えば前年の税額が120,000円だった場合、それを基準に日割り計算を行い、買主から売主へ清算金を支払います。実際の納税通知書が届くのは売却後の4月〜6月頃となるため、その時点で金額に差異が生じる可能性もあります。
差額が大きく出た場合でも、原則として追加請求や返金は行わない旨が契約書に記載されるのが一般的です。そのため、売主は仮精算であることを理解した上で、想定外の差異が出る可能性にも備えておく必要があります。
仮精算を行うことで、取引時の手続きをスムーズに進められるメリットがありますが、税額の変動リスクもあるため、慎重な対応が求められます。正確な納税額は後日通知されるため、その確認と納付も忘れずに行いましょう。
固定資産税の精算に関するトラブルを回避するためのポイント
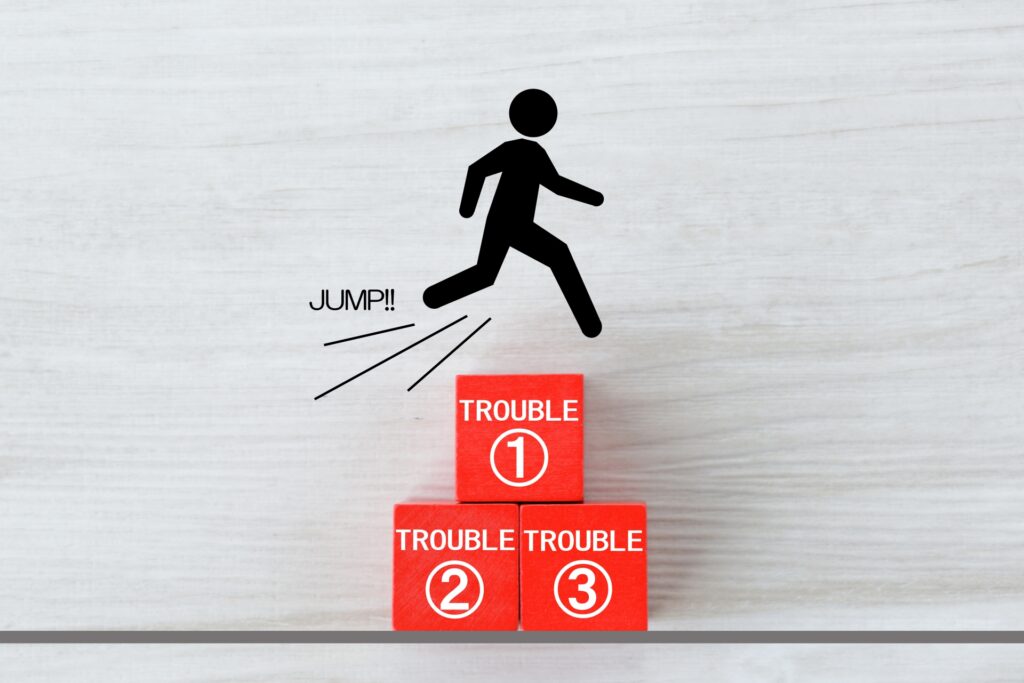
不動産売却において、固定資産税の精算は一般的な手続きですが、認識のズレや説明不足が原因でトラブルに発展するケースも見られます。売主・買主の間で事前に合意が取れていないと、後から不満が生じる恐れがあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、以下のポイントが重要です。
それぞれのポイントについて解説していきます。
売買契約書に固定資産税の精算方法を明記する

固定資産税に関する精算トラブルを未然に防ぐには、売買契約書に精算方法を明記することが重要です。多くの取引では、固定資産税および都市計画税を「日割り」で精算する旨が記載され、計算の起算日も明確にされます。
契約書に精算の詳細が明記されていれば、引き渡し後にた誤解を防ぐことができ、万一のトラブル発生時にも法的な根拠として機能します。
特に注意すべきなのは、精算の実施自体に法的義務がない点です。契約書に記載がなければ、後から請求や交渉をしても相手の同意がなければ支払い義務は発生しません。そのため、口頭だけの確認ではなく、必ず書面で明記しておくことが必須です。
不動産会社のサポートを受けながら、精算条件を整理し、納得のいく契約書を作成することが理想的です。
前年課税額による仮精算を了承しておく

固定資産税の納税額は、毎年4月〜6月頃に自治体から送付される納税通知書で確定します。そのため、売買契約や決済のタイミングでは、その年の税額が未確定であることがほとんどです。この場合、前年の課税額をもとに仮精算を行うのが通例です。
仮精算とは、前年の納税額を日割りして売主・買主の所有期間に応じた金額を算出し、決済時に清算金として受け渡す方法です。しかし、実際の課税額が前年と異なる可能性があるため、仮精算額と実際の納税額に差が出ることもあります。
この差額について、後から追加請求や返金を求めることは基本的に行われないため、事前に「仮精算で確定とする」旨を双方で了承しておく必要があります。契約書にその旨を記載しておくことで、売却後に想定外のトラブルを防ぐことが可能です。
登記と引渡日のズレに注意する

不動産売却における固定資産税の精算では、「引渡日」と「所有権移転登記日」のズレにも注意が必要です。一般的に固定資産税の日割り清算は「引渡日」を基準に行われますが、税務上の所有者変更は登記完了日で判定されます。
こうした混乱を避けるためには、契約書に「固定資産税等の精算は引渡日を基準とする」旨を明記しておくことが有効です。また、引渡し日と登記日を可能な限り一致させるようスケジュール調整するのも、トラブル回避につながります。
登記と引渡しのタイミングを正確に把握し、精算条件を明示することで、双方の納得感ある取引を実現できるでしょう。
山陰エリア(松江市・出雲市・米子市)でおすすめの不動産売却会社

山陰エリアで不動産売却を検討している方にとって、信頼できる不動産会社を選ぶことは重要です。地元の市場に精通し、実績が豊富な会社を選ぶことが、納得のいく売却を実現するポイントです。
以下では、山陰エリアでおすすめの不動産会社を2社紹介します。初めて売却を検討する方にも安心して相談できる会社ですので、ぜひ参考にしてください。
ハウスドゥ松江・出雲・米子(西日本ホーム株式会社)

ハウスドゥ松江・出雲・米子を運営する西日本ホーム株式会社は、山陰エリアに密着した不動産売却サービスを提供している企業です。
| 項目 | 詳細 |
| 屋号 | ハウスドゥ 松江・出雲・米子 |
| 会社名 | 西日本ホーム株式会社 |
| 本社 | 〒690-0049 島根県松江市袖師町2-32 TEL:0852-24-7703 URL:https://www.nn-h.com/ |
| ハウスドゥ 松江 | 〒690-0017 島根県松江市西津田5-1-1 TEL:0852-33-7778 URL:https://www.housedo-matsue.jp/sell |
| ハウスドゥ 出雲 | 〒693-0004 島根県出雲市渡橋町3-2 TEL:0853-31-4010 URL:https://www.housedo-izumo.jp/sell |
| ハウスドゥ 米子 | 〒683-0804 鳥取県米子市米原7-15-27 TEL:0859-30-3100 URL:https://www.housedo-yonago.jp/sell |